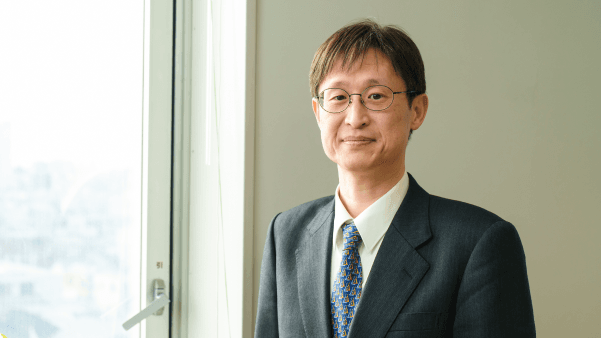有田 亮太郎(ありた りょうたろう) 教授
東京大学大学院理学系研究科物理学専攻 教授 博士(理学)
特定国立研究開発法人理化学研究所 創発物性科学研究センター チームリーダー
有田亮太郎先生へのインタビュー - Share Your Story
[取材・編集] 研究支援エナゴ
「(論文の)引用回数は研究成果の重要性をはかる一つの指標に過ぎず、自分はまだ不特定多数の若い方々に広くアドバイスができる立場にはいない」。今回のインタビューをお願いする弊社からのメールに対する有田先生の最初のお返事です。これまでに発表した論文が合計で20,000回以上引用されている研究者であり、多くの留学生を受け入れる熱心な教育者としての顔も持つ研究者の謙虚な姿勢に感銘を受け、益々お話をお伺いしたいと思いました。
計算物質科学の魅力は?研究者が海外の研究機関に滞在する最大の価値は?お話を伺う中で見えてきたのは、おそらく「人間のやること」に惹かれた幼少期からの、有田先生のヒューマニストとしての姿勢でした。
研究仲間と喜びや悲しみを分かち合いながら、時に体調を崩しながらも業績を残し続ける物理学者有田先生。現在の日本のアカデミアを憂慮し、若い研究者が希望を持てるようになることを切望されています。
少年期に惹かれたのは「人間のやること」
昔の自分を振り返ると、私はラジオを作るのに夢中になったり、星空を見つめながら何時間も過ごしたりといったような典型的な「科学少年」ではなかったように思います。従って「あなたはいつから科学に興味を持つようになったか?」という問いに、何か面白いエピソードをまじえて「幼少期から!」と元気よく答えることはできません。私の場合、大学に進学するまでに少しずつ興味の対象が科学方面になっていった、という言い方が正しいと思います。
むしろ、今思い返すと、高校2年生くらいまで、私は自然現象よりは人間のやることの方に強く興味を持っていたように思います。同じ条件で測定をすればいつも同じ結果が得られるという科学の実験よりは、同じ登場人物でもちょっとしたことで全く違う筋書きにかわるといった話の面白さの方に惹かれていたのでしょう。これを「歴史、政治・経済に興味を持っていた」と大袈裟に言うこともできるかも知れませんが、要は『小説吉田学校』のような本を面白がって読んでいるような生徒でした。

通っていた高校は、裁判官になるとか、(旧)大蔵省の事務次官になる、と言ったようなことを口にする生徒が少なくなく、進路についても、理系への進学をことさら強く推奨するような学校ではありませんでした。高校三年に進級する際、私が親しい友人の一人に自分は進路を理系にすると言った時、その友人が「え?お前は官僚志望かと思っていた」という返事をしたのを覚えています。周囲も私を理系、あるいは「科学少年」として見ていなかったということだと思います。
研究分野を決めた経緯、研究職を志した時期
私が通っていた東京大学の理学部物理学科では、4年生になると研究室に配属され、「演習」と言って研究の見習いのようなことをやります。私は天体のように手を伸ばしても届かないものより、実際に手にとることができるものを研究の対象にしたいと思っていました。それから、計算機の相手を長時間していてもあまり苦ではなかったことから、大規模な数値計算を活かす方向に興味を持っていました。
それで、青木秀夫先生1の研究室を志望しました。当時、青木研究室の助手をされていたのが現在大阪大学教授の黒木和彦先生2です。黒木先生が演習の始まる前や終わった後の雑談の中で物性物理学分野にどういう研究の方向性があるかといった、1995年当時の大まかな地図みたいなものを説明してくださいました。これによって、自分の進むべき方向がぼんやりとイメージできるようになったように思います。青木先生も黒木先生も研究者として尊敬すべき方で、この方々と一緒にやっていきたいと感じたことから、大学院では青木研究室に進学を決めました。

大学4年生のときには漠然と研究職に就こうと考えていたと思います。特に誰かに影響されたということはありませんが、大学院の入学試験の面接の際、青木先生から「あなたは研究者になることを希望していますか?」と聞かれて、迷わずに「はい」と答えた記憶があります。今思い返してみると、その時点ですでに研究者になろうと決めていたのでしょう。1995年当時、私が進学した理学部物理学科では、ほとんどの学生が修士課程修了後に就職するというようなことは考えず、博士課程まで進学してアカデミアに残るのが当然という雰囲気があったように思います。そんな環境で、私も大学院進学時には研究職につくことを考えていたように思います。
計算物質科学の魅力と研究の応用可能性
まだ作られていない物質や、実現が難しい極限環境における物性などをシミュレーションできるところはこの分野の楽しいところだと思います。また、巨人の肩に乗りやすい、という点もあります。手法開発の際、先人が残してくれた蓄積を比較的容易かつ直接的に活用でき、進歩が実感できるのは魅力です。再現性が100%であるところもよいと思っています。同じ手法を使えば誰でも同じ結果がでてくる。分野によっては実験で論文に載っている結果を再現することすら容易ではない、という話も聞きますので。
私が専門としている計算物質科学が目指す具体的な目標に関して言えば、わかりやすい例として室温超伝導の設計・予言が挙げられます。室温超伝導体の発見は物性物理学の究極の夢の一つですし、本当に見つかれば、電力輸送に革命をもたらし得るだけでなく、医療や交通など幅広い分野に応用されるでしょう。
私は、室温超伝導体を実験にさきがけて設計・予言したいと若い頃から言っていたのですが、ある時、そんなことを無責任に言っていると信用を失うと注意されたことがあります。確かに、室温超伝導なんて幽霊みたいなものだ、と思っている人は多いでしょうし、超伝導体について精密な計算をすることは一般にとても難しいです。例えば、物質の化学式の情報だけ与えられて、その物質が一体何度まで冷やしたら超伝導体になるか、という質問に正確に答えるのは簡単ではありません。そもそも、超伝導が発現するメカニズムについて色々な可能性が議論されていますが、それらが一から十まで完璧に理解されているわけではありません。
ただ、最近では、ある種の物質に超高圧をかけると「ほぼ室温といってよい高温」で超伝導がおこることが明らかになってきています。この20年ほどの間に計算技術が発展し、超高圧という極限環境下で室温での超伝導がこの世に存在し得るということが計算で示され、それに対応する実験的観測が実際にできるようになっているのです。ですから「室温超伝導」は全くの絵空事ではなくなってきていると思っています。

国際ジャーナルへの投稿
初めて国際ジャーナルに論文を出版したのは1997年の事で、修士課程を修了するときです。私が所属していた青木研究室では修士論文の成果を国際ジャーナルに投稿するということが普通でしたし、30年たった現在、私の研究室でも状況は大きく変わりません。青木先生も黒木先生も英語に大変強く、私が用意した原稿はいつもお二人にほぼ全て上書きされ、私が書いた部分はほぼ何も残りませんでした。今思うに、言語として稚拙なレベルにあったという以前に、そもそも論理構成が緻密に検討されていなかったのだと思います。
最近は人工知能が優秀で日本語で書くべきことがしっかりと決まっていれば英語への翻訳はさほど大きな問題ではなくなっているように思います。言語の壁が完全になくなって日本人の研究者が国際ジャーナルに日本語で投稿して、論文を日本語で読む日も近い気がします。学生さんにとって今一番大事なことは、英語であれ日本語であれ、筋の通った説得力のある文章を書けるようになることかもしれません。
マックス・プランク研究所での経験
マックス・プランク研究所は大学ではなく研究所ですから、学位を持った研究者、それも自分と年代の近い若手のポスドク研究員が大勢いました。彼らと友達になったことで、お互いに、人生の様々なステージで協力し合えたことが良かったです。情報の交換もできますし、今でも時々一緒に仕事をすることがあります。私に「海外の研究機関に長期滞在する最大の目的は同世代の仲間を作ることだ」とおっしゃった先生がいらっしゃるのですが、まさにそのような経験をさせていただきました。
行く前にその先生に言われたのは、自分のネットワークを作るには2年かかるということでした。1年目は研究を行い、1年目が終わる頃から、それまでにやったことを1年かけて色々なセミナーなどで宣伝して顔を売る。つまり都合2年間かかる、と。
2年間は長い時間ですが、行くと決めてからの時間もそれなりにかかります。私はフンボルト財団に助成を申請しましたが、採用が決まるまで半年かかりました。先生からいただいたアドバイスは、準備が整ってから行こうなどと考えていてはダメで、ある程度見切り発車で行く決心を先にしなさいというものでした。アドバイスをいただいていなければ、のんびりしてしまっていたでしょう。適齢期を逃して海外へ行くチャンスを失ったかもしれません。とにかく期限を定め、この年齢までに海外で研究すると決めなさいというのが、私にとっては大変重要なアドバイスだったと思います。

当時のネットワークがあることで、人材を海外に送り込んだり、海外から人材を受け入れたりすることもできるようになっています。アメリカやヨーロッパでは域内でネットワークができていますが、日本は文化的にも距離的にも孤立しがちです。しかし「あいつの所になら送り出してもよい」という関係ができていれば研究者を送り込んでもらえるし、こちらからの人材を受け入れてもらえます。私が専門としている計算物質科学の分野の場合、個人プレーでやっていると限界があるというところがあり、国際的な共同研究はできるだけ広くやった方が勝ちだと思っています。
私がドイツに行った時、私は青木研究室の助手でした。青木先生が「いい考えだ、行ってきなさい」と背中を押してくださったことについては、本当にありがたいことだったと感謝しています。いま、私はこの時の青木先生の年齢に近づいてきていますが、若い人が海外に行くことについてはできる限りの応援をするようにしています。
研究での行き詰まりについて
研究で行き詰まってしまっている若い研究者にアドバイスを、ということですが、非常に難しい質問です。私自身、若い人とやっている研究が思い描いていた通りに進まずどの方向にいけばよいかわからないとか、面白そうだと思ってやっていたのにそれほどの結果がでなかったとか、一生懸命やっていた研究を誰かにやられてしまったといった問題に日々悩まされていますので。
また、若い時は自分ひとりの問題だったのが、年齢を重ねると成果が出るか否かが研究室メンバーの人生設計に直接関わってくることもあり、問題が一層難しく、複雑になることがあります。あのメンバーの研究がうまくいっていない、こちらのメンバーもうまくいっていない、というように、追い詰められ方がより深刻になることもしばしばです。また、予算を申請して不採択になったりすると、その影響は自分の研究室だけでなく、多くの関係者に及ぶこともあります。いくつになっても研究者である限り何かしら悩みを抱え続けなければならないし、その悩みは深く、複雑になっていくものだと思います。私は幸いにして若い頃ストレスで健康を壊すという経験をせずにすんできましたが、最近はストレスで肺に穴があいたり耳が聞こえにくくなったりして病院にお世話になることが多くなりました。
一方で、年齢を重ねるといいこともあります。研究室のメンバーの数が増えたり、自分の研究室の出身者が新しい研究室を立ち上げたりしてネットワークが広がると、相談できる仲間、助けを求められる仲間が増えます。自分の研究室だけではどうにもうまくいかないところを別グループとのシナジー効果で突破する、といったようなこともよくある話です。
あまりえらそうなことを言えた立場ではないですが、若い研究者に何かアドバイスをすることがあるとしたら、広い視野をもって頼りがいのある仲間をできるだけたくさん作れ、ということかもしれません。司馬遼太郎が小学校6年生の国語の教科書で「自然物としての人間は、決して孤立して生きられるようにはつくられていない。」3と書いていますが、計算物質科学の分野の場合、研究者も個人プレーだけでは生きていけないと思っています。
若い研究者が挫折を体験する、一番よくある出来事として、自信を持って投稿した論文が掲載不可と判定されてしまう、ということがあると思います。先日、共同研究者全員が「よい仕事」と思って投稿した論文がEditorの判断で、査読者にもまわされずにrejectされてしまうという「事件」がありました。第一著者の学生さんからすれば悔しくて寝られなくなるような出来事だったと思います。
こうした経験を若いうちに積み重ねることで、免疫がついてどんどんタフになる人もいれば途中で嫌になってしまう人もいます。私は論文が査読者ではなく、いわゆるハイインパクトジャーナルのEditorにrejectされるのは大した問題ではないと思っています。先日、ある実験研究者と話していたのですが、その研究者の分野の場合、どのジャーナルに掲載されるかが実験結果の信用度につながるのだそうです。そういう分野の場合、確かにハイインパクトジャーナルのEditorに認められることは死活問題です。ただ、私の専門の計算物質科学の場合、本当に価値のある論文は掲載誌に関わらず多く引用されるように思います。ハイインパクトジャーナルのEditorに評価されなくても、コミュニティで時間をかけて評価され、引用され続けるというケースがいくらでもあるため、ハイインパクトジャーナルのEditorに論文を落とされても私はそれほど悲観的にはなりません。

日本の学術研究を発展させるために、社会に求められること
日本の学術研究を発展させるために日本のシステムがどうあるべきか、という質問ですが、これも簡潔にお答えするのが難しい問題です。
先日、ある実験研究者の実験室を見学する機会がありました。この装置は8000万円、あちらは5000万円、日本では最初の導入例だが中国ではすでにたくさん導入されている、などといった話を聞きました。激しい国際競争に勝って最先端の研究成果を出すにはそれなりの資金が必要なのだとあらためて実感した次第です。
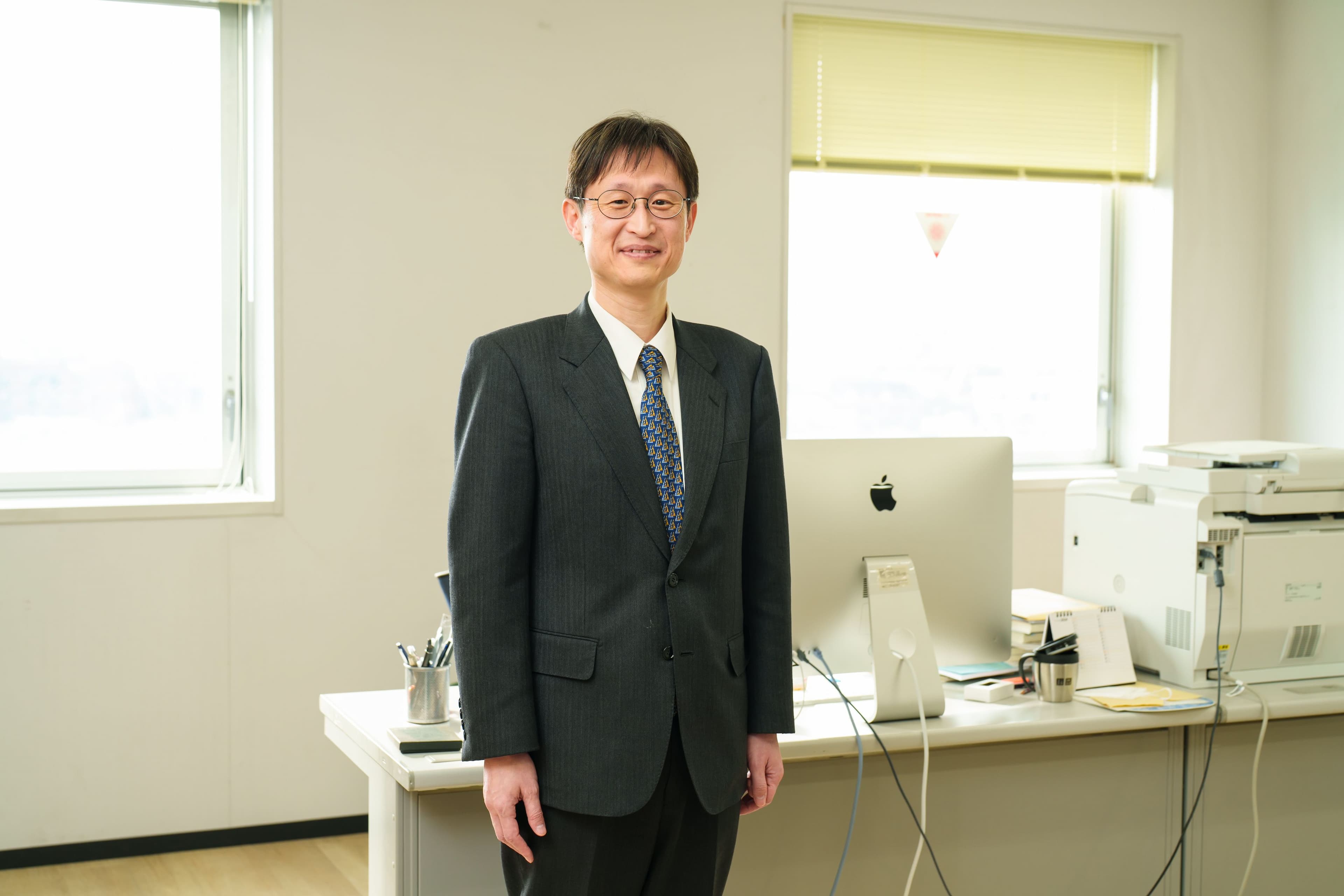
一人の研究者に多額の予算がついたとき、納税者の立場に立つと、その予算によってどんな成果が得られたのか、あるいは得られているのかということは、正確かつ詳細に公開されるべきだと思います。
一方、研究者の立場に立つと、書かなければならない書類が多すぎることによって研究の時間が圧迫されるという状況は望ましくないです。このバランスは非常に難しいと思います。例えば、決められた期間のプロジェクトにおいて、研究開始時の研究計画との整合性を毎年検証して報告することにはそれなりの意味があるとは思いますが、求められる報告書の量が膨大になりすぎると研究者が萎縮してしまうように思います。
当初予想できなかった展開があったときこそ本当の発展があったときですから、計画通りに進んでいなければダメ、という杓子定規な評価ではなく、研究計画の自由な変更も含めて、研究者による自発的、自然発生的な活動を長い目でみてくれるようなシステムがあればいいと思います。
それから、これは研究分野によるのかもしれませんが、日本のアカデミアが若い人たちにとってあまり魅力のある存在でなくなってきているのではないかと危惧しています。私自身、四半世紀前に学位を取得した時、アカデミアのあり方について、こんなことでいいのかと強く問題意識を持ち、アカデミアを離れたこともありましたが、その時からさらに状況が悪くなっているように思います。
立派な業績を挙げているのに学位取得後安定したポジションになかなかつけず、人生設計に支障が出ているといった話を学生さんがあちこちで耳にすると、学生さんが研究そのものには魅力を感じていてもアカデミアには残らないという選択肢を考えるのは当然と思います。研究者の雇用の問題は本当に難しいですが、もう少し若い人が希望をもてるような状況にならないと、アカデミアを支える若い人材が早晩枯渇してしまうのではないかとおそれています。計算物質科学の分野では計算コードがどんどん巨大化しています。国際プロジェクトとしてコードが開発されることもあります。ある世代以降日本がこの輪に入れなくなる、という事態は避けなければならないと思います。
脚注:
1 青木 秀夫(あおき ひでお)。物理学者。東京大学名誉教授。専門は物性理論。
2 黒木 和彦(くろき かずひこ)。物理学者。大阪大学大学院教授。専門は物性理論。
3 『二十一世紀に生きる君たちへ』(「小学国語」大阪書籍刊、1987年)に司馬遼太郎が書き下ろした、子供向けの随筆。