
堂免 一成(どうめん かずなり) 教授
東京大学特別教授室特別教授
信州大学先鋭領域融合研究群先鋭材料研究所特別特任教授
堂免一成先生へのインタビュー - Share Your Story
[取材・編集] 研究支援エナゴ
今回のインタビューの申し入れを快く引き受けてくださった堂免一成先生。「信じたらトコトンやる」を信条に、40年以上の研究生活の中で約800報の原著論文や80報以上の総説論文を発表されています。
「水分解光触媒の創成」という偉業を成し遂げ、光触媒研究の世界的権威とされる先生ですが、学生時代にやりたい研究をやるべく指導教官を説得した際のエピソードや、渡米したとたんに指導教官がサバティカルでいなくなってしまった海外での研究生活の苦労話を大変気さくにお話しくださいました。
研究の行き詰まりを打開するには?日本の学術研究を発展させるため社会に求められることは?研究とその振興に関わるすべての人に最後まで読んでいただきたいインタビューの全文を書き起こしてお届けします。
化学への興味、そして専門分野を決めた経緯
中学の頃から化学を面白いとは思っていました。高校のときに理科系に進むということは決めていましたので、その中のどの分野に進むかを考えており、化学ないしは生物化学、あるいは生物学、の三つぐらいの中から選ぼうと考えてました。
東京大学では、入学すると2年間は駒場での教養課程があります。その教養課程の成績で本郷の専門を決めるのですが、私が入ったのは理科一類で、理学部ないしは工学部に進むのですが、私は空手部に入っていて、当時駒場にあった駒場寮の中の空手部の部室に入り浸って、ほとんど講義には出ませんでした。
そして成績が非常に悪く、ギリギリで駒場を通過しました。一番行きたかったのは生物化学なのですが、そこに行くための点数が足りなかったんです。幸い、理学部の化学科に行くには点数が足りていたので、そこに進んだという経緯です。だから第2志望みたいな感じで行きましたね。もし生物化学系に進んでいたら、今頃はバイオテクノロジーなどの分野に行っていたと思います。
研究分野の魅力
先ほど申し上げたように、私は化学科に行ってからどういうところに進むかを考えたのですが、当時の東京大学理学部化学科に、化学反応学という学問分野の固体の触媒化学を専門とする田丸謙二先生1がおられました。化学反応学という分野が、研究するには非常に面白そうだということと、そしてもちろん田丸先生の講義も面白かったということがあり、そちらに進もうと思ったのです。
田丸先生は生物に近い酵素のようなものの研究もされてると言っておられたので、そこが一番私の興味が重なる部分でした。ただ、生物と関連性が高いといっても、いわゆる固体触媒ですから、有機物をベースとした化学反応の研究の生物の分野とはだいぶ違います。それで、修士課程では熱で働く固体の触媒やその固体の表面の化学反応の研究を主にしていました。
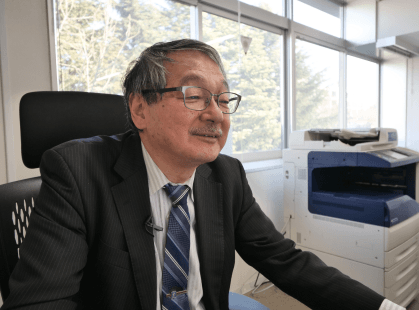
博士課程に進むときに田丸先生にお願いして、今私がやっているような水の分解についての研究を始めました。これは生物体の光合成に非常に近く、水を分解して酸素を発生させるというものです。生物では、酸素とともに、非常に還元力の強いNADPHという分子が作られ、それに二酸化炭素が反応し炭水化物が作られるというのが基本の反応ですが、そこに行く前の光エネルギー変換が起こるのは水の分解です。その反応の研究を勧めてくださったのは、当時田丸研の助手をされていた相馬光之先生2と内藤周弌先生3で、おふたりと話していて、そういう分野があることを知りました。田丸先生は、最初私に博士課程でSurface Science(表面科学)の分野をやらせたかったようですが、先生に無理やりお願いして、田丸研でまだやっていなかったその新しい分野を博士課程のテーマにしていただきました。
水分解を研究する希望を伝えた恩師の反応
研究室で全くやっていなかった新しいテーマでしたから、希望をお伝えすると田丸先生はしばらく、天井を向いたまま考えておられました。10分か20分だったと思いますが、私からするともっと長く感じられました。そして田丸先生から提案されたのは3ヶ月ならやってもよいということでした。その3ヶ月の間に、固体粉末を使って、水が光エネルギーで水素と酸素に分解できたら研究を続けてもよい、と。出来なかったら、田丸先生が最初に考えてた表面科学の研究をやりなさいということでした。その時点で、田丸先生はかなり大きな研究費を取られて、新しい装置を作るという予定がおありだったので、そちらをやりなさいということだったのです。まあ、半分賭けですね。それで、まず3ヶ月という期間をいただいて研究を始めました。
そして3ヶ月後
私がその固体の光触媒で水を分解する前、材料を選ぶ際に相馬先生が助言くださいました。それは、工学部におられた本多健一先生と藤嶋昭先生という先生方が発見されたホンダ-フジシマ効果4についてのもので、これは二酸化チタン光電極を使って光電気化学的に水を分解するという世界で最初の研究です。当初使われていた二酸化チタンそのものだと、外からバイアスをかけないと、光を当てただけでは動かないということはわかってましたが、その後、MITのライトン先生5という方によってチタン酸ストロンチウムという材料で光電極をつくると、光を当てるだけで、外から何もバイアスをかけなくても水が分解することが、ちょうど私が研究を始めようとしたときにはわかっていたんです。それで、チタン酸ストロンチウムの電極ではなくて粉を使って、水が分解できるんじゃないかと考え研究を始めました。私が始めたときはまだ、粉末系で水から水素と酸素を出した例はなかったので、それをベースに研究を始めました。
実は原理的には間違っていたのですが、そのn型の半導体であるチタン酸ストロンチウムの微粒子上に、p型の半導体である酸化ニッケルを組み合わせて、よく太陽電池とかでいうところのp-n Junction(p-n接合)ができるのではないかと最初やってみたのですけれど、そのときは、それだけではうまくいかなくて1回水素還元をしてみました。水素還元すると酸化ニッケルの方だけが還元されて、金属ニッケルになるんですね。金属ニッケルになったものをもう1度低温で酸化させると、酸化ニッケルの表面だけが酸化されるわけです。チタン酸ストロンチウムがあって、金属ニッケルがあって、その上をさらに酸化ニッケルが巻くという構造ができるんですが、それを使い、水蒸気の水を入れておいて光を当てると、酸素と水素が出てきたんです。
これには、3ヶ月も掛からず2ヶ月ぐらいでできたんです。ただ効率はものすごく低いんですね。入ってきた光子の個数に対して何個が有効に水分解に使われるかを表す量子収率ですが、我々が3、4年前に出した論文ではほぼ100%を達成しましたが、そのときは0.1%もなかったと思います。非常に低い。ガスクロマトグラフという酸素と水素を検出できる装置があるんですが、それでやっと見えるか見えないかというぐらいの量しか出てこなかったんです。しかし確かに、水素と酸素が出てきたんですよね。
そのデータを田丸先生にお見せして、確かに約束を守ったから、研究を続けるというお許しをいただいて、博士課程は水分解の研究をすることになったんです。非常にラッキーでした。本当はp-n Junctionなどできておらず、単純に水素が発生するところが、その酸化ニッケルを1回還元した後に再酸化すると、中に金属ニッケルが残っていて表面だけが酸化物になった構造ができ、そこが水素生成活性点として働いていたのです。そのことが実は博士課程の時はわからなくて、その後、東工大に助手として移ってから、さらに詳しく調べてやっとわかった結果なんです。だから、かなりまぐれ当たりなんです。
水分解の研究の社会的な意味
理学部だったということもありますが、私が始めた頃は、純粋に私自身の興味だけでした。
もし太陽の光だけを使って、水が水素と酸素に分解するとなれば、光エネルギーの化学エネルギーへの変換というのが起こるということです。これは自然界では光合成において起きていることで、つまり人工的に光合成ができるということです。そういうことが1マイクロメートルもないような小さな微粒子の上でできるのかというのが、純粋に私の興味だったのです。私が博士号を取ったのは1982年で、その後、20世紀の間ぐらいは、みんなに面白いと言われたのですが、人間社会に貢献できるかというと、なかなかそうはならなかった。ただ、21世紀に入り、化石資源を燃やしてCO2が増えると気候変動が起こるという話がよくされるようになり、化石資源を使わずCO2が増えないようなやり方でエネルギーを作る方法を見つけなければならない、となってきました。次第に、この人工光合成も、その可能性を持つ非常に大きな分野として、世界的に研究が活発になってきました。
国外の研究者との共同研究について
一口に国際共同研究といっても、私の場合、例えば中国や韓国の研究者と行う研究と、ヨーロッパやアメリカの研究者と行う研究では、少し意味合いが異なります。先ほど、本多健一先生と藤嶋昭先生が見つけられた光電気化学的な水分解のやり方に触れましたが、欧米の研究者は主にその方法で研究をする人が多いです。
中国や韓国の研究者は、我々の研究を受け、粉末固体光触媒によって水分解をできるということを知った上で研究を始め、我々と同様、学問の一番基礎になる部分が触媒化学という研究者が多いのです。そのような訳で基本的にやり方が違います。太陽エネルギーを使って光電気化学的に水を分解するか、あるいは粉末を使って光触媒的に水を分解するかという違いです。

欧米の研究者と共同研究するときは、彼らは彼らで基本的には光電気化学的なやり方を研究所でやるんですけども、我々の光触媒でも水を分解できますから、その原理を、一緒に研究するというようなことが多かったです。
中国や韓国の研究者も我々のところに来ますが、私が非常によく研究を共にしたのは大連化学物理研究所にいるLI, Can(李燦)先生です。私よりも数歳若く今はもう非常に偉くなっている彼は、東京工業大学で私が助手をしていた頃に博士課程の学生としてやってきました。その頃の彼自身の研究テーマは水分解ではなかったのですが、中国に帰ってから水分解を研究したいということだったので、装置についての情報に始まり、やり方を全て教えてあげました。そして帰国後研究を始められたのが、光触媒による水分解の研究としては中国で最初だと思います。今の中国では非常にたくさんの人が研究していますが。
ですから、世界のいろいろな人たちと共同研究をしていますが、それぞれ傾向が違いますね。オーストラリアの研究者は、我々が光触媒で水の分解をやるのを知っていて、そのことに興味を持って共同研究をしようとやってきています。つい最近リタイアされた韓国のLEE, Jae Sun先生6という有名な方とも1990年代に学会でお会いして、そのとき先生が水分解に興味があるとのことでお話をし、その後共同研究を始めました。
初めての海外での研究
私が海外に留学したのはIBM Almaden Research Labで、サンノゼにある研究所でした。サンフランシスコの40キロぐらい南にあった研究所で、最初に行った場所が古くなって、滞在した1年半の間にサンノゼの郊外のAlmaden研究所に引っ越しがありました。
そこでは、今の水分解のテーマではなく、レーザーを使った研究をやっていました。固体の表面に分子を吸着させ、それをレーザー光で励起して、その吸着した分子がどういう反応をするか調べる研究です。
IBMの研究所では、1つの研究室を1人の研究員が使います。技術職員と組んで一緒にやるのですが、私が行って2か月した頃に、私が師事した研究室の先生が、サバティカルに行ってしまったんです。日本ではあまりないですが、向こうではサバティカルの制度があり、私が2か月ぐらいいて装置の使い方を覚えた頃に、ドイツに1年間行っちゃったんです。
その間、私1人と、南米ボリビア出身の技術職員の人が残されました。研究室の先生はT. J., Chuangという台湾出身の方でした。海外留学する意味の一つは英語に慣れるということがありますが、私の場合は、その後ずっと電話で1週間に1回、先生と英語で話していたのですが、彼の英語は実はタイワニーズ・イングリッシュなんですね。技術職員の人も、ボリビアン・イングリッシュです。だから私は、アクセントの強い英語しか勉強できなくて、いまだに英語の日常会話は全然得意じゃないです。
例えば大学に留学していれば、学生たちとかなり話をしたはずで、日常会話に不自由なくなっていたと思うんですが、私は1年半いましたが、ほとんどそういう人たちとだけ話して、あとは家に帰ると妻と日本語で話し、IBMの中でも日本人の友達が割といたので彼らとも日本語で喋っていました。だから、あんまり英語は上手くならなかった。
しかし装置を全部1人で使って実験をできたので仕事がはかどり、論文はその1年半の期間だけで1人で10数本は書けたんです。後年、よく学生に「俺1人で真面目にやると、そのぐらいのペースで論文書くんだぜ」というような自慢をしました。装置が非常に良くて、結果もたくさん出たため論文が書けたということもあります。
当時民間の研究所ではIBMの研究所とAT&Tのベル研究所の2つだけに、普通の大学に研究員として行く際に出されるのと同じJ-1ビザ(交流訪問者ビザ)が出てたんですね。そして給料は、IBMやベル研究所の方が大学の倍ぐらいありました。紹介してくださったのは田丸謙二先生なんですが、今探してる人がいるから行ってきたらどうだと推薦してくださったんです。ただ、探している本人がサバティカルですぐいなくなる、という話は聞いていませんでした。
渡米してから知った指導研究者のサバティカル
到着してから1か月ぐらいしてから「俺はもうすぐドイツへ行く」って言うんです。フリッツ・ハーバー研究所のエルトル先生7という、固体触媒の表面化学の分野で非常に有名な先生で後にノーベル賞を取られた方のところに行かれるということだったんで、そういう意味では非常にいいところに行くんだなというのはわかりましたけれど(苦笑)。いなくなるけど1週間に1回は電話でディスカッションできるよ、などといわれて。
実験計画も全部自分で立てました。こういう分子を吸着させ、この波長のレーザーを当て、その後飛び出してくる分子をTime-of-Flight=TOFという時間分解能のある質量分析計で観察するという実験でしたが、やり方や原理を教えてくれて、私が使いこなせるようになった頃に、先生はいなくりました。
英語での苦労について
英語についての苦労は今でもしています。学会で喋ったり、学会の話を聞いたりする分にはほとんど不自由はありません。専門用語については、論文を読んでますし聞いてますから。あと学会の場合、一般的にスライドがあってそれに沿って講演をしたり聞いたりすればいいわけです。だから、それに関しては不自由しないのですが、その後の雑談などでの、特にアメリカの人の、崩れた感じの流暢な英語が私にとっては非常に億劫なんです。国際会議のミーティングで日本人は私だけっていうこともよくあります。そこで外国の人たちが何人かで喋り始めると、フォローするのはなかなか大変です。若い頃は一生懸命フォローしようとしたんですけど、いい加減年取ってくると、もう勝手に喋っていてくれという風になってきました。何か大事なことがあればどのみちこっちに質問してきますから、そのときに何の話だっけと話を聞いて返事するという感じですね。
学術英語や国際環境での学びについて、学生たちへのアドバイス
学生には、海外に行くチャンスがあればどんどん行った方が良いと言っています。我々や、我々よりもさらに昔の先生方は英語で発表するときはすごい大変だったと思いますが、最近の学生はテレビでも英語をよく聞いているし、学校でも英会話の勉強をかなりしています。だから基本的に英語がそこそこできるので、しばらく海外に行っていれば非常に上手くなって帰ってきます。行った人と行かなかった人では差が出るため、海外に行けるチャンスがあったら1年でも2年でも行ってきて、海外の研究のスタイルと共に日常会話を勉強して来いと伝えています。日常会話を不自由なく行うというのは、非常に大事だと思うのです。
ただ、英語の論文を読んだりするのは、普通に日本に居ても、ちょっと勉強してある程度読み慣れてくるとできるでしょう。専門の英語というのは、そんなに多様性がないんですよね。大学入試の英語の方がよっぽど難しい。
ただ、英語で論文を自分で書くことに関しては、必ずしもそうではありません。外国人が書いた日本語はすぐわかりますが、それと同じで、ネイティブの人が書いたのと比べると、日本人が書いた英語はすぐわかるんですね。
最近は英文のチェックをしてくれる会社がたくさんあって、私は東工大にいた頃から、もう20年以上30年ぐらい、同じところに英文のチェックをしてもらってから論文投稿しますので、英語でケチをつけられたということはほとんどありません。そういう仕組みができていますので、日本人が英文の論文書いて投稿するというのもそんなに難しいわけではないですね。当然少しはお金を払いますが、大した値段じゃないですから大丈夫だと思います。
さらに最近は日本語を正確に書いて英文に直すというソフトがありますから、それでもかなりの部分はできるようになってますよね。だから、今後10年もしないうちに、英語を喋れなくても正確な日本語を書ける人が日本語で書いて英語に翻訳すると、ほぼそのまま出しても大丈夫なレベルの翻訳ができるんじゃないでしょうか。だから、日本人の英語コンプレックスというのは次第になくなっていくだろうなと思います。
国際ジャーナルへの最初の投稿から現在に至るまで
田丸先生との約束で行った水分解の触媒の研究をスタートしたのが1979年4月で、1980年にはその最初の論文を発表したのですが、それは私が英語で書きました。私自身は当時としてはちょっと珍しかったのですが修士論文も英語で書いていました。それが実際に論文になったのは、最初の水分解の論文よりもちょっと後ですが。私自身は国語も含めて語学のセンスはなく英語は全然下手なので、一応自分で英語で書いて、それを内藤先生という当時の直接の上司であった助手の先生が直してくださって、さらにそれを田丸先生にチェックしていただいて投稿したという流れです。田丸先生は英語が非常にお上手でしたから、田丸先生が最終的に直してくださったのです。
大学院博士課程のときに論文を6本ぐらいは出しているのですが、田丸先生が英語を最後に直してくださっていたので投稿論文として出すのはあまり不自由なかったんですが、東工大に行ってから出した論文は、そういうチェックがあまり入ってなかったので、投稿した後に、内容はいいけど英語直せという連絡が何回か来ました。
修士論文を英語で書いた理由
私自身の中で、博士課程まで行って研究者になるか、修士ないしは博士課程を終えて企業に勤めるかはちょうど半々ぐらいの感じだったんですが、修士課程で、修士論文を書くための仕事は割と早めに終わったんです。結果的に、フルペーパー論文2本を書けるぐらいの内容があって、だったらもう英語で書いてみたらどうかと、直の上司の内藤先生が、すすめてくださったので英語で書くことにしました。
研究の行き詰まりを打開するには
行き詰まりは、もちろんありますね。ただ、その行き詰まりを打開するためのいわゆるアイデアのストックは、特に若いころには常にいくつか持っていたんです。これをやって駄目だったらこっちやってみようみたいな。だいたいそういうアイデアの10個のうち8個、9個は上手くいかないんですが、さっき言ったように、まぐれ当たりというのが割と多いんです。こういう理屈でこういうことをやってみたら上手くいくんじゃないかと思ってやってみると、実はそういう理屈でなく、別の理由で上手くいっちゃうというようなことが往々にしてあるんですね。
私は助手になったり、准教授になったりしても、学生さんに、こういう理由でこうすれば上手くいくんじゃないかと自分の中で思っているテーマを出したりしていたのですが、ちょっと違う理由で上手くいってしまうということの方が実は多いんですよね。しかも自分の頭の中で考えたとおりに上手くいったときより、進歩が大きいんです。
これまでの経験から言うと、今やってる実験が上手くいかないからといって、そこで悩んでいるよりは、今までやらなかったような他の実験にどんどん手を出していくことで、そこから新しい道が出てくるということが非常に多いです。頭の中で考えて、やっても駄目かもしれないなどとペシミスティックになるのではなく、やってみたら何とかなるとオプティミスティックになる方が、全く新しい分野を開いていくときには大事だと思います。
研究アイデアの着想
自分で実験した結果や、学生さんが持ってくる実験結果を眺めたりする際に、他に様々な可能性があるというのは頭の中に入れておくべきです。実験の結果を見ないと、新しいアイデアというのはなかなか出てこないですから、実験結果をしっかり見ていくというのは一番大事なことです。
田丸先生は、学生時代の私に「夜寝る前にちゃんと研究のことを考えてますか?朝目覚めたときにも考えてますか?」と言っておられましたが、大好きな田丸先生に言われてもシャクなので「大丈夫です、夢の中でも考えています」と答えていました。
実際そこまでは考えていなかったですが、いつも研究の事を考えていると、いろいろ新しいアイデアっていうのは自然に浮かんできますので、それらをストックしておくというのが大事だと思います。そういうストックがないと、研究をやっていても、心細くというか、ペシミスティックになりかけますよね。これが駄目でも、こっちをやれば何とかなる、という精神的なゆとりも大事になってきます。
お酒を飲みながら同僚と話していても研究や実験の議論になります。そういうときに出てくるアイデアもありますし、夜寝ていて目が覚める直前によくいろいろ考えつくようなこともあります。いろんな場面で常に頭の中に研究のことを置いておくと、いろんなところでアイデアが出てきます。夜中に寝ているときに浮かんだアイデアが素晴らしいと思っても、パッチリ目覚めて考えると大したことがない、というようなこともありますけれど。
日本の学術研究を発展させるため社会に求められること
今、日本では研究者の人口も徐々に減っていると思います。女性研究者が少ないというのは元々日本では特に言われていますが、女性研究者は日本だけでなくヨーロッパでも少ないですから、女性研究者はもっと(世界的に)増えるべきだと思います。
日本における研究職の社会的位置づけについて言うと、研究職という職業は、あんまり給与的には恵まれていません。例えば日本の大学の現在の一般的な教授の給与は、大手の企業の30代半ばから後半ぐらいの人の給料と、大差ないぐらいです。東京大学でも、私立大学でも、教授になると年齢相応に60歳近くまではある程度上がっていきますが、その上がり方もそんなに大きいわけじゃない。しかも教授同士の給与の差は、大体プラスマイナス5%ぐらいに収まります。だから一生懸命頑張った先生も、あまり頑張っていない先生も、差がないということと、日本社会全体で給料が安いと言われるなかでも大学の教授の給料があまり高くないということで、研究者になりたがる優秀な人がだんだん減ってるんですよね。
だからその辺のところは大きいかなと思います。あと、企業の研究職に就く人たちの中でも、同じ企業で営業や人事を担当する人と比べ将来的に給与やポジションが上がる人は、多くないですよね。むしろ企業の中でも、研究能力が優れた人には、通常のレベルの人よりも高い給料を払うべきだろうなと私は思います。アメリカや中国では大学でも、研究者のレベルにより、軽くひと桁ぐらい給与に差があります。
そこまでは、日本社会ではなかなか難しいのでしょうが、研究者の高いモチベーションを保つのと、優秀な研究者を大学に残していくという意味では、数倍ぐらい差がついてもよいでしょう。日本社会はあまりにフラットにできているので、大学で研究しても、どうせ教授ぐらいの感じだと会社に入った方がよっぽど給料が良くなると考えてしまうわけです。
笑い話で妻に時々話すのですが、私の家に招いた研究室の学生たちの中に、中国からの留学生がいて、後日、つくづくと言うのです。「先生が中国に来てくれたら今の何倍もいい家に住んで、給料ももっとがっぽりもらえますよ」って。それを聞いて笑っちゃったんだけど、確かにそれは現実で、今の中国だったらいい研究をすると、給料も上がって日本よりも遥かにいい金額を貰え、全然良いとこに住めるということです。日本は少々(すぐれた)仕事をしようが何をしようが大差ないですよね。やっぱり、目の前にぶら下がる人参の大きさが全然違うんじゃないかとは思います。
研究へのモチベーションの維持
私の場合、基本的に研究が好きだというのはあります。
給料は、たくさんもらえればもらえたで当然妻は喜びますから、もらえるに越したことはありませんが、実際は生活に困らないぐらいはもらっています。そして、私の場合、研究費は2000年頃までは非常に大変だったのですが、2000年を過ぎたあたりからは、かなり恵まれている方です。たくさん研究費をもらって研究をしていると、当然プレッシャーはありますが、基本的には研究が面白くてやっているので精神衛生上の問題ということはあまりないですね。
ただ社会的に見ると、優秀な研究者をできるだけ日本の科学技術の発展に持っていくためには、そういう人たちの待遇をできるだけ良くするというのは大事だと思います。企業でも経営者は非常に大変なのでしょうが、経営者だけでは、日本の社会が本当の意味で発展することはできないでしょう。金融機関の人たちは、お金をいっぱい儲けるかもしれないですが、誰のおかげで儲けてるんだと言いたくなる部分もあります。
日本だけの話じゃないかもしれませんが、結局、社会が発展していくための原動力として、研究で新しい技術が出るというところが非常に大きいですよね。それに携わる人たちをもう少し日本の社会は優遇してもいいのではないかと思います。
脚注:
1 田丸謙二(たまる けんじ、1923年11月2日 – 2020年7月22日)は、日本の化学者、理学博士。 専門は触媒化学および表面化学。1963年10月より東京大学理学部化学科の教授を務めた。
2 相馬 光之(そうま みつゆき、1939年-)。専門は分析化学・物理化学。1965年より東京大学理学部助手を務め、その後国立公害研究所(後に国立環境研究所に改組)の化学環境部の部長、静岡県立大学教授などを歴任。
3 内藤 周弌(ないとう しゅういち、1943年- )。専門は触媒。後に神奈川大学工学部教授を務める。
4 酸化チタン(TiO2)に光を照射すると、そのエネルギーによって水が水素と酸素に分解されるという光電気化学反応の一種。発見者の本多 健一(ほんだ けんいち、1925年8月23日 - 2011年2月26日)と藤嶋 昭(ふじしま あきら、1942年3月10日 - )から名付けられた。
5 M. S. Wrighton(マーク・スティーブン・ライトン、1949年-)。光化学を中心とした研究が専門。1970年代よりMIT(マサチューセッツ工科大学)で教鞭を執り1990年より同学のProvost(学務担当副総長)を務めた後、セントルイスのワシントン大学総長、ジョージ・ワシントン大学の名誉総長を務める。
6 韓国の研究者。浦項工科大学教授、蔚山科学技術大学校教授などを歴任。
7 ゲルハルト・エルトル(Gerhard Ertl、1936年-)。ベルリン・フリッツ・ハーバー研究所物理化学科の名誉教授。2007年度ノーベル化学賞受賞。
