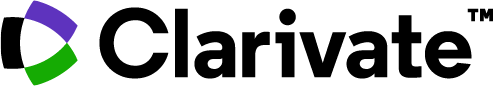―分子標的薬レンバチニブを先行投与しTACEと組みf合わせるという新規治療の開発に成功し、それまでの標準治療に比べて中期肝癌患者の全生存期間が2倍に伸びたと伺いました。治療法の順番を変えるだけで治療効果が格段に上がったのですね。なぜ、他の人はこのアイディアを思いつかなかったのでしょう?
工藤教授:さあ、それは他の人に聞いてみないとわからないですね(笑)。ただ、私は臨床と基礎の両方の下地があったのだと思います。臨床の現場では診断から治療まで全て自分自身でやりますし、TACEの経験もかなりあって、以前は自分1人で週に16件ほどTACEを実施していた時期もあるくらいです。多くの症例に接する中で「分子標的薬の投与のタイミングを早めればTACEの効果が高まるはずだ」と実感していました。

また、基礎研究についても、私は若いころから臨床の論文だけでなく基礎の論文にもしっかり目を通してきました。20年ほど前にScience誌に発表された動物実験で、レンバチニブと似たような薬剤が血管新生を抑制し、腫瘍血管を正常化させ、その結果、薬剤を均一に分布させることができるという報告があったものですから、TACEの前にレンバチニブを投与すればTACEの効果がさらに高まるはずと確信していたのです(工藤正俊教授研究コラム「レンバチニブ先行後の選択的TACEによるシナジー効果」参照)。
肝臓癌研究の世界的権威・学会が新規治療法を引用
―この新しい治療法に対して、周りの反応はいかがでしたか?
工藤教授:肝臓癌の世界的な権威といわれている人たちが、早速、米国の学会でも私の論文を引用し、「新しい治療法の開発」として度々紹介してくれました。またCancers誌に2019年に発表した新規治療に関する論文は、アメリカ肝臓学会(AASLD)のエキスパートパネルが執筆したposition paperである「Trial design and endpoint in HCC(hepatocellular carcinoma)」という論文(2020年Hepatology誌)にも引用され、合理的な新規治療法として紹介されています。実は私もこのアメリカ肝臓学会のエキスパートパネルの共著者なのですが、私の担当部分でないところで別の研究者が引用して、そのように記載してくれていました。

日本肝臓学会の肝癌診療マニュアルの改訂に間に合うタイミングで論文を発表しましたので、日本では、この治療法が浸透しつつありますし、アジア太平洋肝癌学会(APPLE)という国際的な治療方針の指針にもすでに反映されています(Liver Cancer誌2020年に掲載)。
また、世界のあちこちから講演依頼があり、この冬にはニュージャージーに出張して全米の腫瘍内科医向けに講演を行いました。希望者が多くて会場に収まりきらないというので、西海岸から東海岸までの全米をカバーするために2日に分けて4回インターネットでライブセミナーを開催することになったのです。同様の講演会やライブセミナーは今後、カナダ、オーストラリアなどでも予定されていました。しかし新型コロナウイルスの影響で渡航できなかったため全てウェブで私の部屋から、カナダ、オーストラリア、中国、台湾、タイなどに対して、ウェブ講演を行いました。中国では17,500人の医師が視聴しました。
失敗した臨床試験から「宝」を見つけ、活かす
―この治療法のインパクトがいかに大きかったか、皆さんの反応が物語っていますね。ところで世界中の研究グループがこぞってTACEと分子標的薬の併用治療の開発に取り組みましたが、多くの臨床試験は失敗に終わりました。なぜ先生のチームが成功を収めることができたのでしょうか?
工藤教授:レンバチニブがソラフェニブよりも肝臓がんに対する奏効率が高かったことも一因ですが、もうひとつの大事なポイントは、対象となる患者さんを限定したことだと思います。どんなに優れた薬や治療法でも、それが効く人と効かない人がいます。両者を区別せずに臨床試験を行うと、一部の人には確かに効いているのに、全体的に見て有効性を証明できないという結果になってしまうかもしれません。効果が期待できる患者さんに限定して臨床試験を行いポジティブな結果を発表しないと、いつまでたっても「新規治療法」が認められず、せっかく臨床上のベネフィットがあるのに、患者さんはその恩恵を受けることができません。
ポジティブな結果が得られなかった臨床試験の論文は、実は宝の山です。なぜ失敗したのかという視点でじっくり読めば、「この層別因子を入れるとか、あるいはこの集団に絞ればポジティブな結果が得られたはずだ」というポイントが見えてきます。それを熟考して次の臨床試験のデザインに活かしていくことが大切です。今回は、TACEの効果が乏しく、また肝機能を落としてTACEによって恩恵を被らないであろうと思われる集団(腫瘍量の多い集団)のみを対象にして臨床試験を行ったのが、ポジティブな結果を出せた原因であろうと考えています。
膨大な数の論文執筆を可能にする、「書く」習性
―臨床や研究の現場に立ちながら、海外での会議や講演に出かけ、多忙を極めていらっしゃる中、毎年60~100報という膨大な論文を発表していらっしゃいます。どうしてそんなにたくさんの論文を書けるのですか?
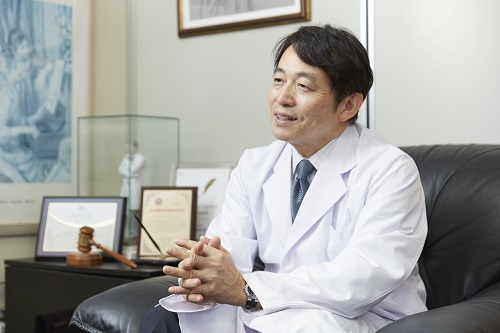
工藤教授:京都大学の医学部を卒業して間もない頃、神戸市立中央市民病院という高度医療と救急が主体の地域の基幹病院に赴任しました。夜の5時から朝の9時までの間に150人くらいの患者さんが救急外来に来ますし、一晩で30-40台の救急車で搬送患者もあるような忙しい病院でした。
私も当直勤務を担当し忙しい毎日でしたが、その頃でも毎朝6時から9時は論文執筆の時間と決めて実践していました。おかげでそのように忙しい市中病院勤務でも18年間に29報くらい筆頭著者の英文論文を書き上げることができました。その習性がしみついているのでしょう。今でも移動中はタクシーの中であれ、飛行機の中であれ、ずっとパソコンで論文を書いています。出張がないときは午前中の時間を執筆に充てることが多いです。若い頃の過酷な経験のおかげでしょうか、集中して論文を書くことが苦になりません。2019年のCancers誌で発表した論文も確か4~5日で書き上げたと思います。
―論文執筆や研究生活の中で利用されているツールがあれば教えてください。
工藤教授:Liver Cancer誌(2019年ジャーナルインパクトファクター9.720)の編集長を務めていることもあって、InCites Benchmarkingを使って研究者の経歴や業績を調べたり、また最新のジャーナルインパクトファクターを自分で計算したりしています。ジャーナルの質を保つためにも、正確な情報を集めるのは重要なことだと考えています。
まずはケースレポートを英語で
―若い研究医の方にアドバイスがありましたらお聞かせください。
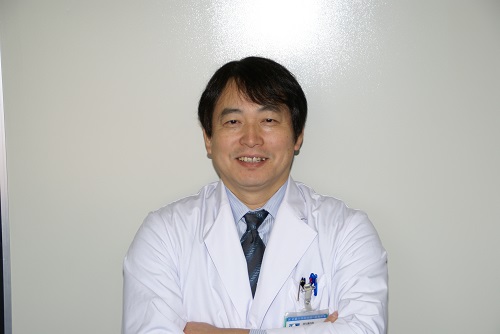
工藤教授:まずは、珍しい症例について、ケースレポートを書くところから始めるのがいいでしょう。その症例に関連する論文を徹底的にリサーチすることになるでしょうから、知識を蓄え論理的思考能力を養ういい機会にもなります。もちろん、書くのは英語です。論文は英語で書かなくては意味がありません。私の教室ではリサーチミーティングも英語でやっています。ケースレポートの次に目指すのはフルペーパーの論文になりますが、最終的には単施設ではなく多施設、後ろ向きではなく前向き試験、国内だけでなく国際的な共同研究を実施して論文を書けるようになるのが理想ですね。
また、医師である以上、論文を書くことだけでなく最高の治療を行うことが最も大切です。最先端の治療を行ってこそ、未解決の問題が見えてくる。そしてその課題解決のために臨床試験を組む。その繰り返しです。臨床研究には終わりがありません。
癌細胞阻害薬を用いた新規治療法の開発へ
―今後の課題は何でしょうか?
工藤教授:免疫チェックポイント阻害薬の効果を検証しているところです。私たちの体には、体内に侵入した異物を攻撃するかどうかをチェックする仕組みがあるのですが、癌細胞はこれを悪用して自身を異物とみなさないよう免疫系に働きかけるのです。
これを阻害するのが免疫チェックポイント阻害薬で、オプジーボが有名です。つい最近、別の免疫チェックポイント阻害薬アテゾリズマブと分子標的薬ベバシズマブの併用の臨床試験が成功しました。私もGlobal Steering Committeeとしてこの臨床試験を主導したのですが、今年中には世界中で使えるようになると思います。また、肝臓癌には同じく免疫チェックポイント阻害薬であるペンブロリズマブも有効とされているので、ペンブロリズマブとレンバチニブを先行投与したTACE併用療法の効果を検証し、中程度の進行肝癌の患者さんに臨床試験を行っているところです。さらに、切除やラジオ波による根治的治療の後の再発抑制に対しての免疫療法の効果というテーマや、免疫療法が効く患者さんと効かない患者さんをあらかじめ見分けられないかというテーマにも取り組んでいます。
―多くの患者さんを救う方法が次々に増えていきますね。ますますのご活躍を期待しております。ありがとうございました。
***
工藤正俊教授へのインタビュー・前編では、肝臓癌治療法の発展の経緯や、世界初となった治療ガイドライン作成の背景についてお話いただいています。