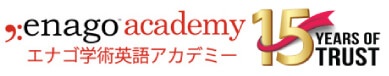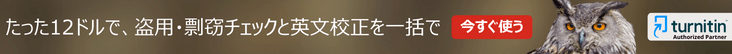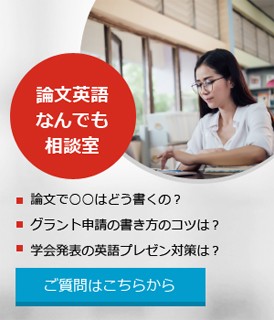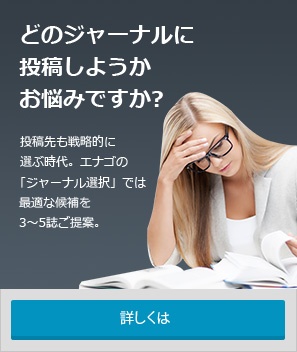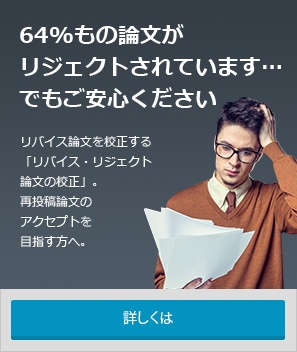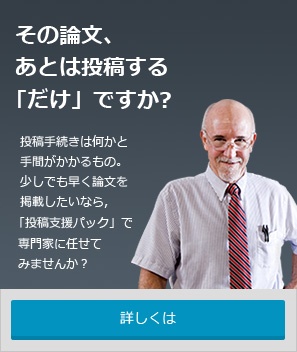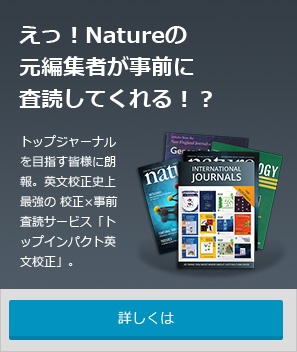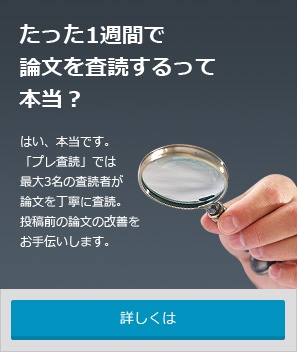論文の考察をクリエイティブに書くには?(前編)

オーストラリア国立大学(ANU)のインガー・ミューバーン(Inger Mewburn)准教授が、大学院で勉学に勤しむ学生さんにお役立ち情報をお届けするコラム「研究室の荒波にもまれて(THE THESIS WHISPERER)」。インガー准教授が論文の考察(Discussion)の部分をクリエイティブに書くためのコツを紹介します。こちらの記事は、前編、後編の2回に分けてお届けします。前半は作家がクリエイティブになるための環境作りをどうしていたかと、インガー准教授が建築業界にいた当時どのように創作性を磨いたかの考察です。
さて、去年私は、How do I write the discussion section? という記事を投稿しました。
この記事を書いたのは、論文執筆に関する検索から「研究室の荒波にもまれて」のサイトを訪れる人の75%が、論文の「考察(Discussion)」の部分について知りたがっていることを示すトラフィック分析があったからです。創造性が必要な「考察」は論文の中でも特にやっかいです。去年の記事では「考察」で何をどのような順序で行うか書きましたが、創造性については触れませんでした。
創造性・クリエイティビティに関する研究はたくさんあり書籍も山ほど出ています。でも、創造性をもたらす万能薬などは今のところ発明されていません。
難しい問題ですね。
では、創造的な研究者になるにはどうすれば良いのでしょう。秘訣は、創造性を何かの出来事やインスピレーションと捉えるのではなく、プロセスとして捉えることなのだと思います。どんな研究者でも、訓練により、必要に応じて創造的になることができると私は考えています。
創造性についての本で私のお気に入りの1冊はメイソン・カリーの著書『Daily Rituals: how great minds make time, find inspiration』(日本語版『天才たちの日課 クリエイティブな人々の必ずしもクリエイティブでない日々』)です。著名な作家、音楽家、エンジニア、建築家、哲学者などの日課がそれぞれ数ページで紹介され、様々なプレッシャーのもと人がどのように創造性を発揮するかが描き出されています。
創造性の追求に積極的な人もいれば、そうでない人もいます。たとえば、ジェーン・オースティンは同じ時代と文化の多くの女性と同様、職業を持つことを期待されていませんでした。彼女には、執筆したり考えたりするための自分専用の場所はなく、家族のスペースでそうした作業を行わなければなりませんでした。 (子育てをしながら博士課程にいる方も親近感を覚えるでしょう)。オースティンの甥によると、彼女は「すぐに片付けられたり、吸い取り紙で隠せたりする小さな紙」に書いていたそうです。執筆中の作品については、他人の目に触れないようドアの傍に座って書き、誰かが来てドアがきしむ音が聞こえたらすぐに原稿を片づけて裁縫を始めるようにしていたといいます。
オースティンと対照的なのが120年後の作家パトリシア・ハイスミスです。ハイスミスは、『Strangers on a Train(見知らぬ乗客)』や『The Talented Mr. Ripley(太陽がいっぱい/リプリー)』など、素晴らしいスリラー小説で知られています。彼女が素晴らしいのは、規則正しい仕事をしながら(毎日3時間から4時間書き続けて2000語を執筆)、同時に非常にだらしない人だったということです。伝記作家アンドリュー・ウィルソンは次のように書いています。
「彼女は仕事モードになるため、ベッドに座って、周りに、たばこと灰皿、マッチ、コーヒー入りのマグカップ、ドーナツ、砂糖の入った小皿などを置いた。制約めいたものを避け、書くという行為を可能な限り楽しいものにしていたのだ。 “自分用の子宮”を創り出し“まるで胎児のような姿勢”で書く、と言っていたということだ。」
(素晴らしいですね。私がハイスミスになりたいです。)
建築業界にいた頃、創造性は向こうからやって来る訳ではないと教えられました。建築学科で学んだことの1つは、行き詰まった際にツールを切り替えるということです。鉛筆で描くのをやめて、スチレンボードで立体模型を作るなどです。それでもだめなら、粘土かプラスチックで模型を作成する、鉛筆ではなくペンで描く、定規を使って描くのをやめてフリーハンドで描く、クレヨンで色をつける、絵の具で上塗りする、コラージュをする、図面を動かしてコピーを取る、等々。建築学科での楽しみの半分は、新しい創造的なプロセスを考え出すことでした。
様々な理由で、私は約20年前に建築の世界を去りました。業界に戻りたいと思ったことはありませんが、そこで培った創造性についての姿勢はそのままです。建築家の仕事というものは、映画などで描かれる苦悩する天才のそれとは対極です。創造のプロセスで感傷に耽っている暇はないのです。腕まくりして、ただ作業を進めるのです。ペンを持ち、ランチタイムまでに建物を描き上げる、それが現実なのです。
必要に応じて創造的になるという技術が身につけば、アイデアがわかないという不安からも解放されます。アイデアを出すのは簡単になりますが、それだけで困難を乗り越えたことにはなりません。デザインのアイデアのほとんどは、ガラクタだからです。
今回はここまで。アイデアの取捨選択や発想の転換、ツールの活用など、続きの話は「論文の考察をクリエイティブに書く(後編)」をご覧下さい。
原文を読む:https://thesiswhisperer.com/2021/03/03/telling-compelling-research-stories/