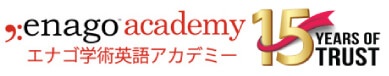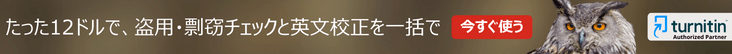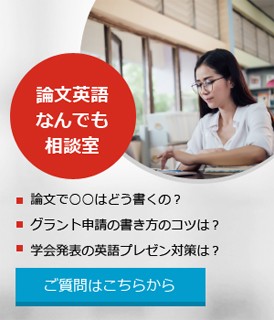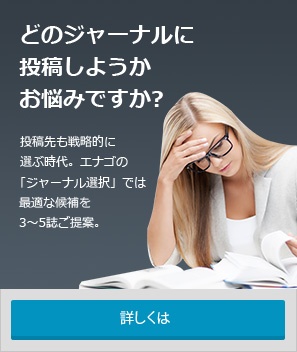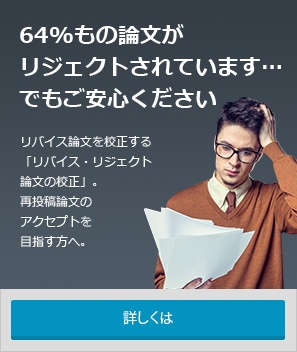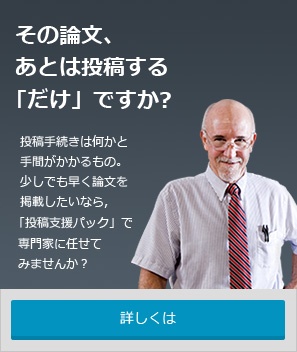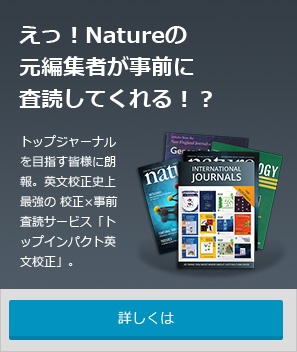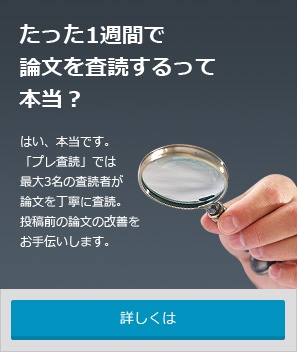学術書や論文のインデックス作成方法

オーストラリア国立大学(ANU)のインガー・ミューバーン(Inger Mewburn)准教授が、大学院で勉学に勤しむ学生さんにお役立ち情報をお届けするコラム「研究室の荒波にもまれて(THE THESIS WHISPERER)」。今回は、インガー准教授が学術書を執筆中にインデックス(索引・見出し)をどうつけるか考えたときのお話です。ここで紹介された本は、インガー准教授が他2名と共著で作成し、2018年12月に出版されています。
読者の皆様。私は今(2018年4月時点)、Shaun Lehmann(ANUの学生向けにさまざまな授業を行ってきた)とKatherine Firth(メルボルン大学で学生向けブログThesis Boot CampのResearch Degree Insidersをとして記事を執筆している)と3人でOpen University Pressより刊行予定の書籍『Writing Trouble(How to Fix Your Academic Writing Troubleとの題名で2018年12月に刊行)』を執筆しています。この本は論文執筆の際の問題を「診断」し、「治療」することを目的としたものです。
この本の内容は、Peta FreestoneとLiam Connellが始めたThesis Boot Camp プログラム(学術論文執筆のための集中講座)を発展させたものです。私たちは、独自のプログラムを開講してきた何年もの間、数多くの学生が卒業論文を仕上げるのに苦労するのを見てきました。研究者としては優秀な指導教官であっても、学術ライティングについて良い指導ができるとは限りません。この本は、悩める学生の声を受けて書かれています。(Thesis Boot Campについては「卒論を1日1万ワード書く方法」でも詳しく紹介しています。)
この本を作成するにあたって、皆さんからコメントをもらいたいと思います。ここで取り上げるのは「Where’s your discussion section?(ディスカッションしているセクションはどの部分?)」につながる部分です。ディスカッション(考察)セクションは、学術論文にはお決まりの、研究の目的を論じる部分。以下にインデックスの作り方について書いていきますが、以前私のブログ「研究室の荒波にもまれて」に投稿した用語集についての記事(ENTER THE GLOSSATORS)にも関連する内容です。Writing Troubleについて興味がある方は、この本専用のメーリングリストに登録してください。(訳者注:現時点では既に本書が出版されているので、内容に関するコメントなどの応募は行われていませんが、メーリングリストへの登録はできるようです。)
インデックスは、用語集と同じ目的で作られるものです。インデックスを作るとなると誰でも及び腰になってしまいそうですが、インデックスとは基本的に、論文や書籍の中に出てくる用語を分かりやすくまとめたものです。用語集同様、読み手にとって最も興味深く、役に立つだろう部分にスポットライトを当てることで、どのようなことが書かれているかを見出しとして示しつつ、伝達する役割を担っています。
インデックスを作成するのは用語集を作成するよりも大変な作業ですが、苦労するだけの価値はあります。インデックスが学術出版で求められているという以上に、分かりやすいインデックスは、読者にその書籍を読む(あるいは買う)気にさせる重要なツールです。本を手にする際、自分の関心のある題材について書かれているか、読む価値があるかを判断するのに、目次や見出し(インデックス)を見たりしませんか?おそらく、ほとんど毎回見ていることでしょう。
3人でこの本を書き始める前にインデックスを作成した経験があったのは、私だけでした。しかも、その出来は最悪。そこで学んだのは以下のような手順を踏む必要があるということでした。
ステップ1: 役立つことをテーマにする
まず、読者が自分の本を買ったり読んだりする理由について考えます。学術書は小説とは違うので、手始めとして実用性に重点を置くのもいいでしょう。読者がどのような問題を解決したいのかを考えるという思考実験です。想定した問題を意味するような単語やフレーズを考えることで、大まかなテーマ(論題)リストが出来上がります。
私の前著『How to be an academic』は、特に非正規雇用の研究者向けの学術界で生き残るための実用的なガイド本です。この本を書いたときには、「お金を稼ぐ」、「ダメな奴らへの対処法」、「スピーディーに書く」などをリストすることから始めました。次に、インデックスを見た人に幅広い題材を扱った本だと印象づけるために大切だと思うテーマを考えました。そこから「networking」といった言葉を思いついた訳です。テーマが絞れれば次のステップ、書籍のどの部分でそのテーマを論じるかを特定する作業に進みます。
ステップ2: テーマに関わる文の塊を探す
このステップが、全体でも一番やっかいな作業です。心して取り組まなければなりません。リストを作り上げるために、すでに飽きるほど読んできたテキストを鵜の目鷹の目で読み返します。そして、本の中でテーマがどのように、どこに記述されているかを書き留めます。ページ数を間違えずに拾い出せるように、最終稿ができてからチェックするのをお勧めします。
テーマに関わる記載のある文の塊が見つかったら、都度、そのテーマに関する単語やフレーズについて考え、ページ番号をメモしておきます。私が最初に原稿を見てリストしたのは次のような語句でした(以下、英単語は原文のまま)。
テーマ:Academic
(以下、関連する単語やフレーズと掲載ページ)
Acronyms, value of 124 – 125
Arrogance 50 – 55
‘Backstage work’ 226, 236
Bookshelves 306
Cleverness 46, 49, 250 – 251, 255 – 257
Cultural Capital 46 – 47, 89 – 90, 245
Dinner Parties 56, 60, 64
Competition 260
Fashion 85 – 90, 306
Gift economies 253 – 254
Hiring practices 62, 229 – 236
Love of the work 18, 76, 264, 288 – 291
Migrants 56 – 60
Salaries 31, 222
‘service’ 101
The new normal 39, 229, 231
Academia as a Bad Boyfriend 16 – 19, 32 – 33, 36, 231
Academic journals, questionable practices of 156 – 162
Academic hunger games 13, 229
ADHD 67
Amabile, Tessa 46
Aaron, Rachael 198
Architecture as a profession 28, 218
Baby Boomers 283
Becker, Howard 125, 153 – 154, 193, 195 – 196
Bullying 52, 54 – 55
テーマ:Blogging and social media
(以下、関連する単語やフレーズと掲載ページ)
The purpose of the Thesis Whisperer blog 9
Time implications of blogging 12, 177
Starting blogging 22
Mark’s simple rules of blogging 38
Safe Spaces? 48, 267
Writing posts 82, 263 – 264
Value of sharing for your career 112, 220, 303 – 304
As open access publishing 154, 159, 220 – 222
Enjoyment 256, 263
Mainstream media shit storms 268 – 269
Social media shit storm 284 – 285
実は、この作業の途中で細かい作業を自分で行うのを断念し、NVivoというテキスト分析ソフトを使い始めました。このソフト、役には立つのですが、使いこなすスキルがない人にはお勧めしません。使いこなせるようになるのに時間がかかるので、原稿提出の締め切りに間に合わない可能性が大です。
ステップ3: テーマにこだわり過ぎない-提案は却下されることもある
私は、ステップ2で作りあげたインデックスを出版社に提出しました。すると、リストを受け取った出版社の担当者が何週間もかけてまとめ上げ、著者である私の努力に敬意を表しつつもプロの編集者に渡しました。そして戻ってきたインデックスは、どうなっていたか。最初に提出したものとは完全に別物になっていました。例を挙げると、私は「Dinner Parties」を、academicというテーマの中に入れていました。かなり大雑把なくくり方です。最終版のリストではアルファベット順に整理され、「D」の項目に「dinner party」と修正されていました。
(こちらの本に興味がある方は「THE THESIS WHISPERER」の本の紹介記事をご覧下さい)
私がこのとき学んだこと?それは、アルファベット順でリストを作成するのであれば、一貫してアルファベット順で並べるのがベストということです。テーマにこだわり過ぎたのが敗因でした。単純にキーワードをアルファベット順に並べれば良かったのです。そしてもうひとつ。仕上げとして、互いに関連性のある語句を考え、それらが関連あると示唆するように「see also」として表示しておくのも有用な手です。
これで作業はおしまいです。ね、論文執筆の問題の「治療」に薬はいらなかったでしょ。必要なのは、せいぜいコーヒーぐらいのはずです。
これが私流のインデックスの作り方です。もっと洗練された方法もあることでしょう。上手な方法を知っている、という方はぜひ、コメントをください!
原文を読む:https://thesiswhisperer.com/2018/04/11/how-to-make-an-index-for-your-book-or-dissertation/