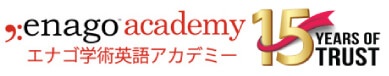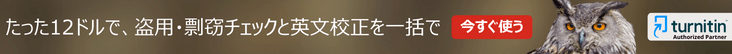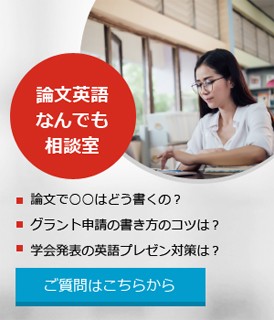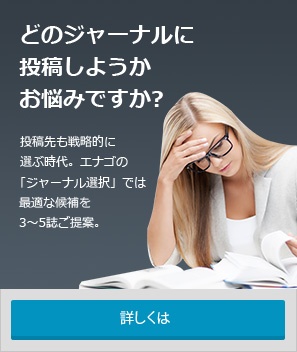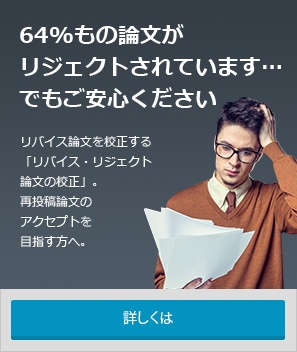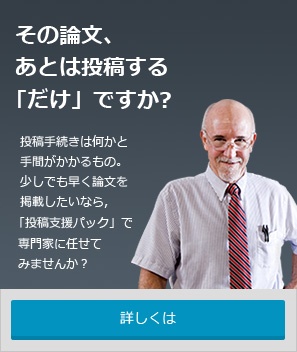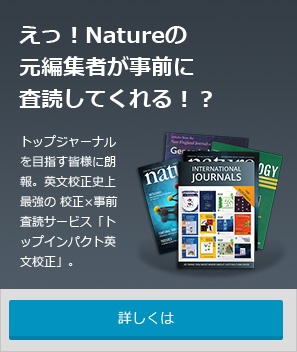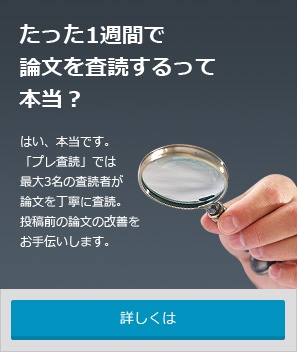金子智紀氏へのインタビューー「ケアする / される」から「ともに生きる」社会へ

日本初の学術系クラウドファンディングサイト「academist」を運営するアカデミスト株式会社が実施する、若手研究者を対象とした研究費支援プログラム「academist Prize」。エナゴが協賛する同プログラム第4期の採択者である、慶應義塾大学SFC研究所上席所員で、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科後期博士課程在籍中の金子智紀氏に、書面インタビューでお話を伺いました。
1.「パターン・ランゲージ」と呼ばれる「知の記述方法」を、「思考の補助具」として活用することで介護のより良い実践を促進する研究を行われています。いつごろ、どのようなきっかけで今の研究テーマに興味を持たれましたか?
最初に「介護」に触れたのは、中学の時の怪我とリハビリ経験がきっかけでした。その後、高校に進学し、生徒会活動の一環で介護施設でのボランティアを経験。そこで介護現場の現状や、介護人材不足と制度の崩壊リスクといった「2025年問題」を知り、「自分が最期を過ごしたいと思える介護とは?」という問いが生まれました。
成城大学進学後、その思いはさらに強くなり、パターン・ランゲージという「知の記述方法」と出会います。パターン・ランゲージとは、よい設計やよい実践における共有パターンを言語化(ランゲージ化)したものです。介護分野にも応用できると確信し、パターン・ランゲージ研究の第一人者である井庭崇先生に学ぶため、慶應SFC(湘南藤沢キャンパス)への再受験を決意。
猛勉強の末、2014年にSFCに入学。1学期目から井庭研究室に所属し、認知症とともによりよく生きるための工夫をパターン・ランゲージで記述するプロジェクトに参加しました。全国で活用していくために、学部3年生の頃には、RUN伴と呼ばれる認知症の当事者、家族、地域の方々が参加するイベントの事務局として全国を回り、現場の実情を徹底的に調査しました。その結果、「自分が最期を過ごしたいと思えるケア」に出会い、具体的な研究領域が見えてきました。
介護は環境や状況、個々の症状によって常に変化するため、「これが正解」や「よい介護とは〇〇である」とトップダウン的に定義することは難しい。しかし、だからといって、他の実践から何も学べないわけではないはず。というのも、全国の介護現場を回る中で、「あそこの介護はいいよね」と言われる施設には、共通する特徴があると感じていたからです。ボトムアップの視点で優れたケアを実践している施設を調査し、その共通項を示すことで、多くの人の実践を支援できるのではないかと考え、「やはりパターン・ランゲージしかない」と思いました。井庭研究室では、いきなりプロジェクトを持つことができないので、学部での経験を踏まえて、修士課程でプロジェクトを正式に発足させました。
2. academist Prize 第4期にアプライした理由は何ですか?
博士論文の執筆に専念できる環境を作るため、academist Prize 第4期にアプライしました。申請したタイミングでは、3人の子育てをしながら博士論文の執筆に取り組んでおり、研究に集中できる環境を整える必要がありました。 そのため、論文執筆期間中は講師業や仕事を減らし、研究に専念するための資金を確保したいと考えました。
また、卒業後の活動も見据えて、研究を社会に還元しながら持続的に継続していく基盤をつくりたいと思っていました。博士論文を完成させるだけでなく、その成果を広く届け、社会実装につなげることを見据え、academist Prizeのプラットフォームを活用しながら、支援者とのつながりを強化し、研究を続けるための仕組みをつくりたいと思ったからです。
3. 実践者が何を行っているのか、そして介護職員を支援するためには何を伝えれば良いのかを特定して「思考の補助具」を制作されるとあります。具体的にどのようなステップで課題や解決策の特定を行っていますか(調査依頼の方法、対象となる施設の数、現場での滞在期間、など)?また、これまでに、あるいは現在進行形で、その際に経験された困難や、予想外の出来事などはありますか?
「ともに生きることば」の作成にあたって、まずは実際の介護現場に足を運び、フィールドワークを重ねることから始めました。介護職員や管理者の方々にインタビューを行い、現場でどのような実践がなされているのか、どのような工夫や課題があるのかを丁寧に記録しました。その語りを整理し、パターン・ランゲージの形式で文章化し、それぞれに名前をつけ、視覚的に理解しやすいようイラストも制作しました。その後、異なる施設の職員や関係者にもフィードバックを依頼し、内容をブラッシュアップ。ここまでが修士課程での研究のプロセスです。
 パターン・ランゲージの作成プロセス(※修士課程)
パターン・ランゲージの作成プロセス(※修士課程)
博士課程では、さらに現場での実証と検証に重点を置きました。実際に「ともに生きるケア」を実践している介護職員の方々からフィードバックをもらい、現場での活用方法を探るためのユーザーテストも実施しました。また、自身も約1年間、介護現場で働きながら、実際の業務のなかで「ともに生きることば」がどのように使われ、どんな影響をもたらすのかを検証しました。こうしたプロセスを通じて、現場で活用しやすい形に落とし込むことを意識しました。
 パターン・ランゲージの作成プロセス(※博士課程)
パターン・ランゲージの作成プロセス(※博士課程)
予想外の出来事としては、2020年の新型コロナウイルスの蔓延です。介護現場をフィールドにしていたため、感染リスクの観点から施設への訪問ができなくなるという問題に直面しました。そこで、2020年3月から約1年間、知り合いの介護施設に住み込みで働くという選択をしました。外部からウイルスを持ち込まずに調査を継続するための対応でしたが、それだけでなく、高齢者と同じ目線で暮らし、実際にケアスタッフとして働くことで、フィールドワークでは得られない学びを得ることができました。
4. 支援金を研究の事業化に向けて活用されるとのことです。どのような事業を構想されているかお聞かせいただけますか?
2025年1月8日に一緒に研究をしてきた後輩と一緒に「非営利型株式会社KOTOBUKI」を設立し、研究の成果を社会に還元しながら、新たな事業の形を模索中です。国内向けと国外向けのサービスを検討中です。
国内向けには、「ともに生きることば」の内容をベースにしたオンラインプラットフォームの開発や、介護職員向けの研修・ワークショップの実施を構想しています。これまで全国170以上の介護施設・3,500人以上の介護従事者に向けた研修を行ってきましたが、今後はより体系的に学べる場を提供したいと考えています。このアイデアや活動が評価され、経済産業省 OPEN CARE PROJECT AWARD 2023「OPEN IDEA」部門で部門賞を受賞しました。
海外向けには、日本国内の実践知を発信し、視察の受け入れや国際連携を促進する事業も計画しています。日本の介護現場で培われた知見を海外の福祉現場と共有することで、新たな収入源を確保し、日本の介護の持続性にも貢献できると考えています。この取り組みは、先日「TOKYO MOONSHOT ビジネスピッチ ザ・ファイナル」で最優秀賞を受賞しました。
5. 超高齢化社会を迎え、介護そのもの、そして介護現場における労働環境・処遇改善のニーズは一層高まっています。ご自身の研究成果をいつか政策提言としてまとめて、国に提案するお考えはありますか?
はい、研究を通じて得られた知見を政策提言という形で活かしていきたいと考えています。ただ、介護政策は国レベルだけでなく、市区町村単位でも実施できることが多いと感じています。介護保険制度の運用は市区町村ごとに行われるため、地域ごとの取り組みを支援する形で「ともに生きるケア」の実践を広めることが、現場に即したアプローチになるのではないかと思っています。
また、「ともに生きる」という視点は、単なる介護技術の向上にとどまらず、地域全体の支え合いやケアのあり方そのものを見直すヒントになります。まずは、自治体や介護事業者と連携しながら、小さな成功事例を積み重ね、それを国全体の政策にもつなげていくような形で、ボトムアップの政策提言を模索していきたいです。そして、その成功事例は、これから高齢化社会に入る国にも政策提言をしていきたいです。
6. 日本の介護事情は海外のそれと比べてどうでしょうか?日本から海外の現場に発信できること、あるいはその逆のパターンなど、ご意見をお聞かせください
日本の介護制度や実践は、もともとヨーロッパの仕組みを参考に発展してきました。しかし、日本独自の進化を遂げたことで、今では逆にヨーロッパから日本の介護現場を視察するケースが増えてきています。特に、日本の介護施設における認知症ケアの実践は、海外から大きな注目を集めており、高齢化が急激に進むアジアの国々からの関心も高まっています。
調査をしていると、「え、認知症の方なのに、縛らなくて大丈夫なんですか?!」といった驚きの声を聞くこともあります。実際、海外の介護現場の多くは、日本の20〜30年前の状況に近く、これまで日本が培ってきた実践知を発信することで、他国の介護の発展を支援できる可能性があると感じています。そのため、日本の介護実践を海外へ発信し、視察の受け入れや国際連携を促進する事業を計画しています。
一方で、日本が海外から学ぶべき点もあります。海外の介護現場は「課題解決型」の思考が強く、エビデンスに基づいた実践(エビデンス・ベースド・プラクティス)が重視されています。日本の介護は、自立支援や共生を重視した独自のモデルとして発展し、多くの実績を上げていますが、「ケアのあり方」に関する科学的エビデンスの体系化はまだ発展途上です。特に、心理的支援や関係性の構築に関する実践は評価が難しく、現場の経験知に頼る傾向が強いのが現状です。「複雑なものを簡易化する」のではなく、「複雑なものを複雑なまま理解する」ことを、研究によって支援したいと考えています。
7. 今後の研究のご予定を差支えのない範囲で教えてください。また、Academistのウェブページの自己紹介にある「社会の医者(Doctor)」として、今後、介護以外の現場を対象に研究を実施される予定はありますか?
「正解のない世界だからこそ、社会の問題を直すDoctorになりたい」 ー そう考え、自らの手で社会の課題を解決するための「道具」を開発することを目指して、博士課程に進学しました。これまで私は、介護現場における「ともに生きるケア」に注目し、「ケアする/される」という一方向の関係性ではなく、「ともに生きる」関係性を築くことが、より良いケアにつながるという視点から研究を続けてきました。
今後は、この「ともに生きる」というテーマを、介護にとどまらず、子育て・教育・パートナーシップといった領域にも広げていきたいと考えています。人々がともに気にかけ(ケア)、ともにあろうとする関係性を築くことは、持続可能な社会の基盤になるはずです。複雑な時代において、特効薬のような即効的な解決策ではなく、漢方のように根本から改善する処方箋が必要だと思っています。そのために、研究を論文執筆だけで終わらせるのではなく、社会に還元し、実装していくことが不可欠です。卒業後は、研究と実践の両輪で活動を続けながら、新たな社会の「処方箋」を生み出していきたいと考えています。
8. 金子さんの研究活動の原動力やインスピレーションは何ですか?
私の原動力は、「次世代に何を残すか?」という問いです。 介護の課題について話を聞くたびに、「どうして何十年も前から指摘されているのに、解決されていないのか?」という疑問を持ってきました。特に今、介護人材不足が深刻化し、制度の持続可能性が危ぶまれる中で、課題はより顕在化しています。自分にも子どもができ、「彼らが将来自分の介護のために夢を諦め、介護離職を余儀なくされる社会にしてはいけない」と強く思うようになりました。だからこそ、今できることとして、介護の現場で培われた知見を社会全体に広め、未来の世代により良い介護環境を残すための仕組みを作ることに取り組んでいます。
インスピレーションの源は、現場での対話です。施設の利用者やその家族、地域で暮らす高齢者の方々、施設経営者、ケアスタッフなど、さまざまな立場の人たちとの対話の中で、現場のニーズと自分が持つシーズの掛け合わせが起こり、新たな研究や事業のアイディアが生まれます。
9. 研究で行き詰まりを感じる時の対処法は?
インスピレーションの源とも重なりますが、私は「現場に行くこと」を最も大切にしています。 研究室でデータを整理したり、論文を執筆していると、どうしても視野が狭くなったり、思考が堂々巡りしてしまうことがあります。そんなときこそ、介護施設の現場に足を運び、利用者の方やケアスタッフの声を聞くことで、新しい気づきや研究のヒントを得ることができます。実際に、「ともに生きることば」の作成過程でも、壁にぶつかるたびに現場に戻り、そこでの対話を通じて研究を深めてきました。研究は、社会をより良くし、課題を解決するための手段であると考えています。だからこそ、現場の声を聞きながら、実際に役立つものにしていくことが欠かせません。
10. 日本の学術研究を発展させていく上で、社会に求められることは何でしょうか?
いろいろなことが必要だと思っていますが、研究の成果を社会に届けるための支援が増えることで、発展していくと思います。例えば、研究成果をもとに起業を支援するための仕組みが整うことで、研究が進むだけではなく、社会全体がより良くなると思っています。
研究を支えるのは大学や研究機関だけでなく、企業や行政、市民社会との連携も不可欠です。研究と実践がつながる環境が広がることで、新しい価値が生まれ、日本の学術研究の可能性がさらに広がっていくと信じています。
11. 最後に、博士課程に進もうか迷っている修士・学部生にアドバイスをお願いします
博士号は研究者としてのゴールではなく、スタートラインだと思っています。自分も今年(2025年)の3月にスタートラインに立ったばかりです。私の恩師である井庭崇先生が、「博士号は研究者のパスポートだから、早く取りなさい」と、慶應SFC初代環境情報学部長の相磯秀夫先生によく言われていたそうです。私自身もこの言葉を受け継ぎ、博士課程への進学を決意しました。また、学部の卒業式(2018年)で、総合政策学部の学部長だった河添健先生が「迷ったらカオスな方法を選びなさい」と話されていたのが印象に残っています。その言葉通り、私は「正解のない世界」に飛び込み、介護という領域で研究を続けてきました。
博士課程の4年間は、研究だけでなく、家族と向き合う時間でもありました。2021年、今のパートナーと出会い、2人の子どもと一緒に暮らし始めました。その後、2023年に長女が生まれ、3人の子どもを育てながら研究を続け博士論文を仕上げました。
正直、研究と子育てを両立できていたか分かりません。むしろ、子育てが本業で、限られた時間の中で研究をやり切るしかなかったというのが実感です。しかし、その状況だからこそ、「この時間で論文を書き切る」といった強い覚悟が生まれ、一人だったら持てなかった焦りが、研究を推進するエネルギーになっていました。
博士課程への進学に迷っている人に伝えたいのは、博士の進学を応援してくれる人や、研究を届けたいと思える相手がいるなら、進んでいいということです。博士課程は決して一人で完結するものではなく、周囲を巻き込みながら進んでいくもの。その準備ができていれば、どんな困難があってもやり抜くことができるはずです。パスポート(博士号)は早めに取っておきましょう!!
クラウドファンディングサイト「academist」の金子さんのページはこちら。クラウドファンディングに挑戦する理由や現在取り組まれている研究課題についてお話しされています:
https://academist-cf.com/fanclubs/355
こんな記事もどうぞ
櫃割仁平氏へのインタビューー「美は世界を救う」を心理学で実証したい
渡部 綾一氏へのインタビューー意識の発達の多様性を解明し、子どもたちが生きやすい社会を目指す!